
ミャンマー・長期化する軍政の支配と困窮する市民生活
~ミャンマー市民を襲う空爆、地雷の脅威~
清水 俊弘 JCBL 代表理事
JCBLは昨年度より、ミャンマー国内で人道支援活動をする現地NGO、Dove K.K.(DKK)を新しいパートナーとして、軍政下のミャンマーで暮らす人々に対する人道支援を続けています。昨年は、山間地で避難生活を送る国内避難民に対する支援が中心でしたが、加えて今年は増加する地雷被害者への支援も本格化しました。2023年12月にタイのメーソットにて、DKKのメンバーと活動の進捗状況を確認しましたので、以下に報告します。
◇ミャンマーの地方民族自治地域の現況
2021年2月1日のクーデターから2年と10カ月が経過、軍政は「非常事態宣言」の延長を繰り返し、軍主導の選挙実施を目論んでいるが、民主派の抵抗も激しく、公正な選挙実施の見込みは全くない。
民族自治の強い地方では、乾期に入り政府軍と民族武装組織の戦闘が激化している。一部メディアでは民族統一軍(NUG)や各地に林立した人民防衛軍(PDF)の巻き返しが報じられているが、ロシアや中国からの軍事支援を受け圧倒的な装備で勝る政府軍はカヤー州、カイン州、シャン州などの市街地にも空爆や遠隔砲撃を繰り返しており、街はゴーストタウンと化している。カヤー州の州都ロイコーでは、政府軍の攻撃により11月以降だけで少なくとも12人の子どもを含む76人が死亡、70人以上が負傷している。主のいなくなった商店では政府軍兵士による略奪行為が常態化しており、軍政が地方山間地を統治できる見込みは全くない。

◇地雷被害の増加と DKK/JCBL によるサバイバー支援

混沌としたミャンマー情勢の中で、地雷による被害者数を正確に把握することは困難だが、2023年4月の段階ですでに全国で388人の被害者が確認されており、昨年1年の被害者(390人)に迫っていたことがわかっている(UNICEF)。
また、2023年度中には政府軍が使用したクラスター爆弾による被害もシャン州、カイン州、カヤー州などで確認されている。
政府軍は、PDFやNUGの兵士が田畑や山林を移動することを知っているため、そうした場所に多くの地雷を埋めている。避難先で、野菜作りを始める人が増えている中で、耕作中に地雷を踏む農民が増えている。
KNDF(カレンニー民族自衛軍)のリハビリテーションセンターに登録されている地雷犠牲者は現在52名。全てが男性で、うち65%にあたる34人が市民である。残りは元兵士で、すでに兵役から外れている。
ディモソの高校に通うソー・ドー君(16歳)は、戦闘から逃れるため、両親と共にワリカウク地区に移住し、そこでトウモロコシ栽培の作業労働者として働くことになった。収穫の作業を始めて3日目、畑に埋められていた地雷を踏み、両足を失い、意識不明の重体で病院に運ばれた。サッカーが好きだった彼は、両足を失った自分の未来が受け入れられず、深刻なうつ状態になり、何度も自殺を試みた。そんな彼に、DKKは治療費を支援、義足がつけられるように適切な治療を受けることができた。切断面の状態が良くなるにつれ、彼は本来の明るさを取り戻し、今では失った自分の足をジョークのネタにするほどまでに回復した。

生計を立てるために
JCBLが支援した1万ドル(約150万円)のうち、約100万円が地雷犠牲者(サバイバー)のために使われた。支援はリハビリテーションセンターにいる52名のサバイバーにそれぞれ希望を聞いたうえで配分された。現在の「異常事態」の長期化が予測される中、サバイバーにとって必要なことは、家族を養う手段を確保することだ。
最も多かったのは、家畜飼育で20名に対して約42万円が鶏や子豚の購入費、小屋作りなど。次に多かったのは、菜園造りの取り組みで、19名に対して約40万円が、農地の借地料や種や肥料の購入代などに使われた。
収穫した野菜は自分たちの食材になる他、多くの避難民が利用するペキン市場で販売され、幾ばくかの現金収入にもなっている。ペキン市場は大規模ながら急峻な山間の中にあり、政府軍の偵察機が近寄れないので安全だとしている。

また、菓子や日用雑貨などを販売する小売店やバイクや自転車の修理小屋を開きたいと希望する人も10名おり、全体で約20万円(個々に約2万円)が開業資金として配分された。どの取り組みにおいても言えることは、混とんとした政情下でも生活を続けられることを第一に考えた支援になっていることだ。
購入した子豚は繁殖させ、増やすことができる。野菜も各種栽培することで販売収益を上げることができる。
地雷で片足を失ったバウ・レーさん(35歳)は、3人の子を持つ父親だが、足が不自由になったため、収入を得る仕事ができなかった。彼は、小売店の開業を希望し、JCBLから約2万円の支援を受け、菓子や日用雑貨を仕入れた。最初はとても小さな屋台で品数も限られていたが、徐々に売り上げを伸ばし、屋台は当初の倍の大きさになった。
彼は「足を失ったことで、生きる希望もなくしていたが、この店を始めて再び家族を養うことができて生きていく自信が湧いてきた」と語っている。
残りの支援金は、政府軍の砲撃によって大怪我をした子どもたちの治療費や避難民村での子どもの補助栄養食配給に充てられた。

◇山間地の避難民支援

DKKが活動する、シャン州南部とカヤー州周辺の避難民村の点在地域。JCBLが支援していたKNHWOの工房があったのが、ロイコー(カヤー州の州都)、そこから車で1時間ほど下ったところに同州第二の町ディモソがある。ディモソから西側山間部、シャン州との州境付近に多くの避難民村が点在し、DKKのベースもその近くにある。
プルーソには、約2,000人が滞在する最大の避難民村があり、KNDF(カレン民族自衛軍)のリハビリテーションセンターもここにある。
同地域では、DKKを含め複数の人道支援グループが活動、支援地区や内容については、月に2回開かれる「キャンプ・コミッティ」で調整される。キャンプは、山間地に点在するため、医療支援や物資輸送は人力での運搬が中心となっている。
DKKは引き続き、移動診療や子どもたちへの教育支援、補助栄養食配給などを行っている。JCBLからの支援で子どもたちへの補助栄養食として牛乳が配給された。

◇若者の未来を奪う国軍の資金源を断つこと
メーソット滞在の最終日、カレン民族の負傷兵を保護する施設を訪ねた。狭いコンパウンドの中に、無数の簡易ベッドが並び、大怪我をした若者たちが手当てを受けていた。何人かから話を聞くと、彼らはクーデターの前は皆大学生だったという。本来であれば、何らかの職業につき、家庭を持つ頃かもしれない。しかし、軍の暴挙が彼らにあったはずの未来を奪った。
この政府を支え続けている日本政府やいくつかの企業の姿勢にも怒りを禁じえない。政府軍の暴力的支配から一日も早く市民の安全を取り戻し、公正な政治プロセスへの軌道修正を促すためにも、引き続き現状を訴え、メコン・ウォッチらと協調し、国軍の活動を支えるあらゆる資金源を断つ行動も必要だ。
ランドマインモニター 2023
国別レポート・ミャンマー編

最新のランドマインモニター 2023 に掲載された国別報告から、ミャンマーに関する部分の主な点について、以下に紹介します。
ミャンマーは、対人地雷全面禁止条約(オタワ条約)への参加に関心を示し、2022 年に同条約を推進する国連総会の年次決議に賛成票を投じたにもかかわらず、対人地雷の製造と使用を続けています。また、ミャンマーの非国家武装組織(NSAG)も、被害者自身が作動させてしまう簡易即席地雷などの対人地雷を製造・使用しています。ミャンマーでは、2022 年から 2023 年にかけて、携帯電話基地局、鉱山採掘、エネルギーパイプラインなどのインフラ周辺を含め、新たな地雷の使用が急増しました。
Ka・Pa・Sa(カ・パ・サ)として知られる国営企業であるミャンマー国防製品産業は、MM1、MM2、MM3、MM5、MM6 の少なくとも 5 種類の対人地雷を製造しています。例えば、2023 年 8 月、カチン独立軍(KIA)と地元の人民防衛軍(PDF)は、シャン州メービン郡にあるミャンマー国軍の前哨基地を掌握した後、MM2 およびMM6 対人地雷を設置しました。
◇非国家武装組織(NSAG)による生産・移転・備蓄
ミャンマーの NSAG は、被害者自身が作動させてしまう簡易爆弾(IED)や破砕型対人地雷を製造しています。このような武器も、工場で製造されたものか、現地で入手可能な材料から即席で製造されたものであるかに関わらず、オタワ条約によって禁止されています。
ミャンマーの一部の NSAG は、クレイモア型指向性破砕地雷、対車両地雷、取り扱い防止装置(除去妨害装置)を備えた対人地雷も製造しています。
2022 年から 2023 年にかけて、ミャンマーの NSAG は即席の簡易地雷を生産し続けており、それ以前にも秘密の武器市場から地雷を入手したり、埋設地帯から除去した地雷を再利用したりしてきました。
◇残虐行為 / 強制的な地雷対処法
モニター編集部は、ミャンマー国軍が地雷の設置が疑われる地域で、民間人を「ガイド」として部隊の前を歩かせ、地雷を効果的に爆発させる行いを継続している証拠を得ました。
これは国際人道法と国際人権法の重大な違反です。2023 年 3 月 21 日、モン州チャイクト郡キンモンチャウン村の軍事キャンプ近くでポーターが地雷の爆発で死亡 し ま し た。2022 年 10 月14 日、 チ ン 州 テ デ ィ ム 郡区のハインジン村とムアルベン村の住民数人が、人間の盾として使われるためにミャンマー軍に拘束されました。
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は 2023 年 8 月、ミャンマー国内武力紛争により国内避難民が合計 190 万人いると報告しています。戦闘が継続する中、地雷対策は何も実施されておらず、地雷原であることを示す目印もないため、ミャンマーの避難民は帰還時に生身の人間自身が地雷探査装置となってしまう可能性があります。
◇被害状況:
ミャンマーには、地雷や ERW(戦争時の爆発性残存物)の死傷者に関するデータを収集する公式なメカニズムがなく、ミャンマーにおける地雷 /ERW の死傷者の総数は不明のままです。
モニター編集部は、2000 年から 2022 年末までに合計6,174 人の死傷者(死者 1,059 人、負傷者 4,994 人、生存結果不明の 121 人)を記録しています。
2023 年 1 月 13 日、バゴー州タウングー郡区のタン・モエタウン村で、女性が道路脇に仕掛けられた地雷を踏みました。地元住民は爆発音を聞きましたが、国軍の規制により立ち入ることができず、犠牲者は血を流して死亡しました。同年 2 月 26 日、カチン州ワインマウ郡区のヌムリ・フカ村とヌワン・フカ・ズップ村の間にミャンマー国軍部隊が設置したとみられる地雷を踏んで少年 3 人が負傷しました。
ユニセフ(国連児童基金)がミャンマーで実施した地雷と ERW の事故に関する報告書は、上記のような被害を含め、2023 年もミャンマーの死傷者が著しく増加し続けていることを示しています。同報告書によると、2023 年1 月から 4 月までの間に合計 388 人の死傷者が報告されています。これは前年の 2022 年の年間犠牲者にわずか 4 カ月で迫っていることを示しています。
(翻訳:清水俊弘)
『 ラ ンド マ イ ン モ ニ タ ー 報 告 書2023(Landmine
Monitor Report 2023)』要旨
ウクライナ、ミャンマー、シリア、イエメンで新たな犠牲者が増加
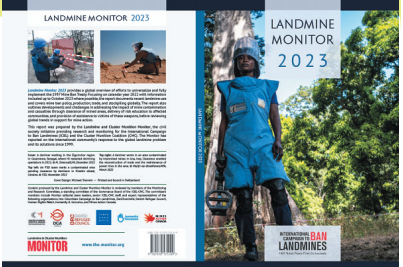
11月20日から24日までジュネーブの国連で開催された対人地雷全面禁止条約(オタワ条約)第21回締約国会議に先立ち、ICBLによる「ランドマインモニター 2023」報告書が発表されました。
今回の注目点を以下に紹介します。
◇対人地雷の新規使用が増加
最新の報告によると、4,710人が地雷によって負傷または死亡し、2022年には、49 の国と他の2つの地域で戦争の爆発性残存物(ERW)が発生した。2022年に記録された地雷とERWの死傷者の85%を民間人が占め、その半数は子ども(1,171人)だった。年間死傷者数が最も多かったのはシリア(834人)とウクライナ(608人)だった。
ウクライナでの紛争のさなか、同国では2021年と比較して民間人の地雷とERWの死傷者数が10倍に増加した。イエメンとミャンマーは、2022年に500人以上の死傷者を記録した。対人地雷の新たな使用は、規範に対する最大の挑戦の1つである。
ランドマインモニターの最新報告書によると、2022年に対人地雷を使用したのは締約国ではないミャンマーとロシアである。ロシアは2022年2月にウクライナに全面侵攻して以来、対人地雷を多用している。
ウクライナ当局は、ロシア軍の支配下にあった2022年、ハルキウ州イジウム市周辺で対人地雷を使用した部隊の状況を調べている。
少なくとも5カ国(コロンビア、インド、ミャンマー、タイ、チュニジア)の非国家武装グループ(NSAG)も、報告期間中に対人地雷を使用した。さらに、アフリカのサヘル地域または国境を接する国々のNSAGによる新たな用途も報告されている。
「紛争が激化し、民間人がその影響の矢面に立たされている世界において、地雷の根絶は、その苦しみを終わらせるための重要なステップであることに変わりはありません」と、地雷除去の専門家であるカトリン・アトキンスは述べている。「地雷除去は、オタワ条約の目指す目標や義務であるだけでなく、人道的義務でもある」。
◇埋設地雷の除去
モニター報告書によると、60の国とその他の地域が対人地雷で汚染されている。
これには、地雷禁止条約第5条に基づく除去義務を負っている33の締約国と、22の非締約国、その他5つの地域が含まれる。アフガニスタン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カンボジア、クロアチア、エチオピア、イラク、トルコ、ウクライナは、2022年に100km²以上の汚染地を報告し、汚染レベルが最も高い締約国である。ウクライナでは、現在進行中の紛争が既存の汚染に拍車をかけている。
1999年に対人地雷禁止条約が発効して以来、合計30の締約国が、自国の地雷汚染地域の除去を終えたと報告している。影響を受けた締約国は、2022年も汚染された土地の除去作業を継続し、合計で219.31km²を除去し、169,276個の対人地雷を破壊した。2022年に除去が完了した土地の約60%は、カンボジアとクロアチアの2カ国だけで占めている。
◇資金不足が懸念される犠牲者支援
医療と身体的リハビリテーションサービスは依然として資金不足の状態にある。
アフガニスタン、スーダン、ウクライナ、イエメンなど、支援を必要とする多数の地雷被害者を抱えるいくつかの締約国では、医療制度の大規模な混乱が報告されている。
2022年は2021年比で52%増加し、世界の地雷対策資金は増加傾向にあるものの、地雷汚染が小規模な締約国では依然として支援を欠いている。報告期間中に地雷対策に割り当てられた総額9億1,350万米ドルのうち、18%がウクライナでの地雷対策活動に充てられている。被害者支援に充てられる資金は2021年と比較して47%増加したが、それでも地雷対策資金総額の5%に過ぎない。
新たな地雷使用によって被害者が増えている現状において、被害者の権利がしっかりと補償されるよう、支援のための資金が確保されることは極めて重要である」と、被害者支援報告担当編集者のローレン・ペルシは強調している。
参 考: www.the-monitor.org |www.icblcmc.org |MineMonitor |monitor@icblcmc.org
(翻訳:清水俊弘)
対人地雷全面禁止条約(オタワ条約)第21回締約国会議報告
清水 俊弘 JCBL 代表理事
オタワ条約第 21 回締約国会議が、2023 年 11 月 20 日から 24 日までジュネーブで開催されました。今回の議長は軍縮会議のドイツ常駐代表のトーマス・ゲーベル大使が務めました。
以下、今回の締約国会議で議論された重要なポイントの概要です。
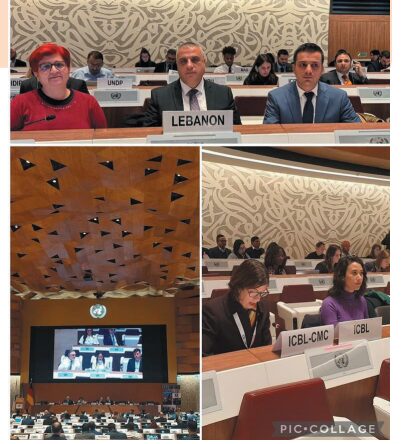
*対人地雷の使用 :
多くの代表団が、一般論として、いかなる状況下でも、いかなる行為者による使用にも反対すると発言しました。しかし、締約国であるウクライナによる使用の報告と徹底的な調査の必要性について明確に言及した締約国はほとんどありませんでした。
今回の最終報告書の地雷使用に関する項で、対人地雷の使用に対する一般的な非難や、調査への言及や、それについて報告する必要性すら含まれなかったことはとても残念なことです。
ICBL はウクライナ代表団と何度も協議を行い、来年 6月の会合間会合までに調査を実施し、結果を報告するようウクライナに求めてきました。この要請を同国政府にしっかりと受け止めてもらえるよう今後もフォローアップしていく予定です。
*第 5 条(埋設地雷の除去)に基づくウクライナの延長要請 :
ウクライナは、2033 年 12 月 1 日までの 10 年間の延長を要請し、認められました。ウクライナの延長要請に関する議論は、今回の締約国会議における最も困難な点の 1つでした。
第 5 条実施委員会(議長:フランス)が 5 年間の延長を提案し、ICBL を含む少数の代表団がこの提案を支持しましたが、ウクライナはロシアとの紛争状態にある中で、この提案に難色を示しました。妥協案としての最終決定は、ウクライナが 2028 年に予定されている第 25 回締約国会議にて、 a) 延長要求が認められてからの進捗状況を含む国内状況の詳細な概要、b) 残された課題、c) 2033 年12 月 1 日の期限までにこの課題に対処する計画をそれぞれ提示すること、さらに、2024 年 4 月 30 日までに地雷リスク教育の計画を含む最新の詳細な作業計画を提出することが合意されました。
*第 5 条の延長プロセスと実施 :
第 5 条実施委員会は、今秋に実施された「第 5 条の延長申請プロセス」に関する協議後に「対人地雷禁止条約 -延長申請プロセス」と題する文書を作成しました。これと並行して、多数の締約国及び利害関係者は、第 5 回運用検討会議に向けて、地雷対策のプロセスを強化し、地雷の除去完了に向けて最善の方法を引き続き検討する必要性を表明しました。
オタワ条約締約国は、2025 年までにすべての仕事を終えようという目標を共有していますが、現実問題として、未だ多くの埋設地雷を抱える締約国の中で、2025 年の完了目標を達成できるのはごくわずかであることは明らかです。
*第 5 回再検討会議、第 22 回締約国会議に向けて :
2024 年 11 月 25 日から 29 日までカンボジアのシェムリアップで開催される第 5 回運用検討会議(Review conference)の議長に、カンボジアのリー・タック(Ly Thuch)上級大臣兼カンボジア地雷対策・被害者支援庁(CMAA)第一副長官が就任しました。それまでの間に、6 月と 9 月にジュネーブで 2 回の準議会議を行うことが確認されました。
また、2025 年 11 月末から 12 月上旬にかけて、第 22 回締約国会議が予定されていますが、市川富子駐日軍縮会議日本政府代表が議長を務めることになっています。
『クラスター爆弾モニター報告書2023
(Cluster Munition Monitor 2023)』要旨
クラスター爆弾関連の情報をまとめた『クラスター爆弾モニター報告書 2023』が第 11 回クラスター爆弾禁止条約締約国会議(9 月 11 日~ 13 日)に合わせて発行されました。同条約の現在の締約国数は 112 カ国、署名国は 12 カ国です。
主な注目点は以下の通りです。
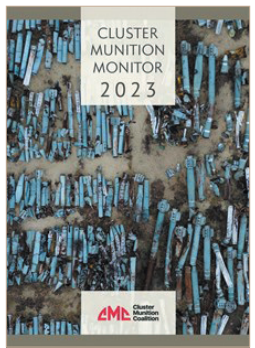
◇クラスター爆弾の使用
2008 年 5 月に条約が採択されて以来、いずれの締約国もクラスター爆弾の新たな使用に関する報告はありません。今回のモニター報告書の調査期間(2022年8月~2023年7月)においては、ウクライナで広範囲に使用された他、ミャンマーとシリアでも新たな使用が確認されました。ロシアは2022 年 2 月 24 日にウクライナに侵攻して以来、クラスター爆弾を繰り返し使用しており、ウクライナ軍もクラスター爆弾を使用しています。
◇死傷者と汚染
世界全体では、2022 年に 8 カ国で少なくとも 1,172 人のクラスター爆弾による新たな死傷者が出ました。これは、モニターが 2010 年に報告を開始して以来、クラスター爆弾による死傷者数としては最多となります。
2022 年の総死傷者のうち、987 人がクラスター爆弾攻撃によるもので、その大半(890 人)はウクライナで記録されています。これらの多くはクラスター爆弾攻撃による直接的な犠牲ではなく、不発弾によるものです。クラスター爆弾の不発弾による死傷者は、2021 年の 149 人に対し、2022年には世界で少なくとも 185 人に上りました。死傷者全体の 95% を民間人が占めており、同不発弾による死傷者の71% を子どもが占めていることが、年齢とともに記録されています。
◇備蓄の破壊と保持
2008 年の条約採択以来、締約国はそれぞれが宣言したクラスター爆弾備蓄の 99% を共同で廃棄し、クラスター爆弾148 万発、子爆弾 1 億 7850 万発を廃棄しました。
ブルガリアは 2023 年 6 月、備蓄していた最後のクラスター爆弾を廃棄しました。条約締約国であるブルガリア、ペルー、スロバキアは、2022 年から 2023 年上半期にかけて、少なくとも 4,166 発の備蓄クラスター爆弾と 134,598 発の子爆弾を廃棄しました。
◇クラスター爆弾不発弾の除去
2022 年、締約国は、約 93 ㎢のクラスター爆弾で汚染された土地を除去し、主に不発子爆弾を含 む 75,725 個の不発弾を破壊したと報告しました。
締約国の中で不発弾汚染国であるイラクは 2028 年まで、モーリタニアは 2026 年までなど、当初の除去期限の延長を要求しています。これらの延長要請はいずれも、2023 年 9 月に開催される同条約の第11 回締約国会議で検討・決定される予定です。
◇生産
クラスター爆弾を製造する、あるいは製造する権利を留保している国は 16 カ国ありますが、いずれもこの条約の締約国ではありません。ロシアは 2022 年も新型クラスター爆弾の生産を続けており、その中には 2022 年初頭からロシア軍がウクライナで使用している少なくとも 2 種類の新型クラスター爆弾が含まれています。
米国では、クラスター爆弾の最後のメーカーが 2016 年にクラスター爆弾の生産を終了しました。しかし、米国は、条約で禁止されているクラスター爆弾の定義に当てはまる可能性のあるクラスター爆弾の代替品を今も開発・製造しています。
◇移転
ウクライナは 2022 年からクラスター爆弾の供与を公に求めています。2023 年 7 月、米国は備蓄していたクラスター爆弾を多数ウクライナに移転すると発表しました。今回移転されたクラスター爆弾は、「不発弾」または不発弾の故障率が 2.35% 未満とされていますが、米国はこの数値がどのようにして達成されたのかを説明していません。これに対して、少なくとも 21 カ国の各国首脳や政府高官が、米国がクラスター爆弾をウクライナに移転する決定を下したことに対して懸念を表明しました。
(翻訳:清水俊弘)
JCBL事務局だより
クーデター後の軍政下でも継続する日本のODAを停止させるべく、ミャンマーに関わるNGOが2023年12月1日に、日本政府に対してODAと公的資金の供与停止を求める要請書を提出しました。ミャンマーの地雷被害者支援を続けるJCBLもこの書簡に賛同しました。
以下、要請の概要です。
日本政府はクーデター以降、ミャンマー軍に対し、暴力の即時停止、拘束された関係者の解放、民主的な政治体制の早期回復を求めると繰り返し述べています。しかし、「事態の推移、関係国の対応等の状況を注視しつつ、引き続き、検討を進める」との回答を各所で繰り返し、具体的にどのような対応をとっているか明らかとはしていません。同時に、7千億円にも上る政府開発援助(ODA)の円借款事業や、軍と繋がりのある民間投資への支援を継続しています。
また、ヤンゴン博物館跡地再開発事業(通称:Yコンプレックス事業)は、ミャンマー最大都市ヤンゴンで、陸軍が所有する軍事博物館跡地に大規模複合不動産を建設・運営する事業で、これに国土交通省所管の官民ファンドである海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)が出資している他、財務省所管の輸出信用機関である国際協力銀行(JBIC)が融資しています。事業の土地の賃貸借契約は、現地パートナー企業と兵站局幹部との間で結ばれており、賃料は兵站局が管理すると見られる口座に支払われ、軍が利用可能な資金となっています。
今回、海外からの賛同も得て、要請書「ミャンマー軍を利するODAと公的資金供与事業の停止を日本政府に求めます」を外務省、財務省、国土交通省に提出し、同日夜に官邸前で日本政府に向けてのアピールを行いました。日本政府が実施中のODA事業については人道支援を除いて一旦すべて停止すること、また、Yコンプレックスについては、国土交通省が直ちにJOINの出資を引き揚げ、財務省もJBICの融資を直ちに取り消すよう、繰り返し、強く求めます。
https://foejapan.org/issue/20231122/15024/
呼びかけ団体:
メコン・ウォッチ、国際環境NGO FoE Japan、武器取引反対ネットワーク(NAJAT)、アーユス仏教国際協力ネットワーク、日本国際ボランティアセンター(JVC)
