
オタワ条約第5回再検討会議参加報告
清水 俊弘 JCBL代表理事
2024 年11 月25 日から29 日までの5 日間、カンボジアのシェムリアップでオタワ条約第5 回再検討会議が(以下5RC)開催された。1999 年に条約が発効してから25 年の節目の開催となった。
参加国は、締約国89 カ国・地域、未締約国のオブザーバー参加12 カ国(米国、ベトナム、ラオスなど)、13 の国際機関、地雷禁止国際キャンペーン(ICBL)等の市民社会組織。

5 年ぶりの完全対面形式となったこともあり、世界各地から集まったICBL のキャンペナーは179 名と過去最大規模となり、また今回の会議に参加した代表団の中でも最大の規模となった。この会議でICBL は、地雷なき世界の実現のために “No exception”(例外無し)“Noexcuse”(言い訳無し)、“No delay”( 遅滞無し) というスローガンを掲げ、すべての締約国がこの意義を共有し、条約の目標を完遂する政治的意思と具体的な計画性を持つことを目指した。
◇条約の規範を守るために
何よりも大事なことは、地雷を使用させないことだ。最新のランドマインモニターにもある通り、現時点で地雷の使用が確認されているロシア、ミャンマーに対して、厳しい非難の声を上げる必要がある。同様に締約国の中で唯一使用疑惑のあるウクライナに対しても、一刻も早い調査結果の報告と条約の義務を守ることを確約させなければならない。
その意味で会議の直前に発表された米国の地雷供与政策については、特に大きな懸念点として会期中を通して最も関心が寄せられた事案だった。
米国による対人地雷のウクライナへの供与の発表が会議に影を落とす一方で、ノルウェー、オーストリア、ベルギー、南アフリカなどの締約国や国際機関などが声明や最終文書で、この憂慮すべき事態に対する懸念を表明し条約の遵守を求めたことは称賛に値する。こうした意見表明をした国々から一様に発せられた「そもそも対人地雷が禁止されたのは、まさにその無差別な性質と壊滅的な人道的および社会経済的影響のためであること」という言葉は、条約の規範を守るうえで極めて重要なメッセージである。
また、条約が採択されたとき、米国がウクライナに送る予定のいわゆる「スマート地雷」を含め、いかなる例外も許されないことをはっきりと確認したことをリマインドする代表団もいた。
様々な締約国から出されたこうした懸念点について、会議に参加していたウクライナ代表団は、「ウクライナの首都に伝える」と一定のコミットメント(受け止め)を示したことを肯定的にとらえたい。

ICBLとして は、ウクライナの自衛権を認め、ウクライナ国民が直面している恐ろしい状況を認識しつつ、ウクライナに対しこれらの兵器を拒否することで条約上の義務を果たすよう強く求めた。併せてICBL は、これらの無差別兵器がすでにロシアの大量使用によりウクライナを含む世界中の多くの民間人に壊滅的な被害をもたらしていることを糾弾するとともに、対人地雷の供与決定を撤回するよう米国に求めた。
併せて会議3 日目から「地雷の使用、移転禁止に一切の例外はない」という趣旨のステートメント(個別の国名は無し)を各国代表団に求めたところ、最終的に25 カ国の賛同を得ることができ、最終文書の一つとして記録された。
このようにウクライナ問題に関心が集まる中、パレスチナ代表団から、「イスラエルはガザやレバノンで地雷を使用している。なぜ誰もそのことに触れないのだ」という発言があり、締約国の中のある種の南北格差を感じる場面もあった。
◇地雷の除去期限の延長審議(第5 条関係)
今年度は、アフガニスタン、チャド、キプロス、ギニアビサウ、ニジェール、ペルー、セルビア、エリトリアの8 カ国から延長の申請が出ている。会議2 日以降のセッションでは5 条委員会のコロンビアの代表から、各国の申請内容についてコメントがあり、またそれを受けての全体審議を行った。もとよりICBL は“No delay”を掲げており、延長するとしても極力最短で終了することを求めている。審議の結果、それぞれの申請が承認された。この中で心配されたのはアフガニスタン(タリバン政権)への対応だった。タリバンを認めていない締約国も多いからだ。ICBL は政権の是非に関わらず、地雷除去を進展させる必要があることから、締約国にアフガニスタンの申請を承認することを求めてきた。結果同国の申請も承認され、延長期間における速やかな除去推進を見守る体制ができたことは良かった。
◇貯蔵地雷の廃棄延長、訓練目的の保有地雷の審議(第
3 条、第4 条関係)
現時点で引き続き1 万個以上の地雷を“訓練目的”として留保している国はフィンランド(1 万5 千個以上)、バングラデシュ(1 万2 千個以上)、スリランカ(7 千個以上)とされている。これらの国以外にも千個から6 千個の範囲で保有し続けている国は22 カ国ある。これらの国々にまずは早急に信管の取り外しと廃棄を進めること、廃棄の詳細な計画を提出することを求める必要がある。
特にフィンランドは、まだ破壊の完了していない貯蔵地雷の数が336 万個もあると言われており、条約からの離脱議論が国内で盛んになっていることを踏まえ、廃棄作業を少しでも前に進めさせる必要がある。同様にギリシャもおよそ35 万個の貯蔵地雷を抱えていることが問題視されている。今会議においても、名指しは避けながらも、こうした義務を遅滞なく実施していくことを求める声が上がったが、新しい行動計画のもとで厳しく監視されていく必要がある。
◇サバイバーの声を届ける
世界中から集まったサバイバー達の積極的参加が、この会議のもう一つの特徴だった。会議2 日目の26 日の朝にICBL が急遽実施した地雷の使用と移転に反対する「無言の抗議」は、世界中のメディアに取り上げられ、25 年に渡って条約を維持してきたサバイバーと彼ら彼女らに寄り添う市民社会の役割を強調した。
ICBL のキャンペナーたちは、オタワ条約が直面する差し迫った課題を浮き彫りにし、全体会議でのメッセージやロビー活動などを通じて大きな成果を上げた。
◇再検討会議の成果文書
今会議では、2019 年にオスロで開催された第4 回再検討会議以降の5 年間の条約の運用・締結状況等を記録した「履行状況報告書」、オスロ行動計画に続く今後5 年間の行動指針「シェムリアップ・アンコール行動計画」と締約国のコミットメントを謳う「シェムリアップ・アンコール宣言」( 政治宣言) が採択された。
政治宣言では、議論の末、条約第1 条で掲げる「いかなる状況下においても、いかなる関係者に対しても、対人地雷の使用、生産、開発、貯蔵、移転を直接的、間接的に行ってはならない」という文言を記し、改めて条約の目指すところをしっかりと確認する内容となったことは良かった。
注目すべきは、長年懸案だった(過去に支援の資金がほとんど受け取れず)適切な支援を受ければ比較的短期間で地雷除去を終了できる可能性のある被災国を支援することを目的とした、自発的な信託基金の創設を検討することが行動計画に含まれたことだ。
シェムリアップに集まった国々は、犠牲者の数が高水準で続いていることを考慮し、今後数年間でリスク教育にもっと注意を払う必要があることにも同意した。これらの措置は、条約の規範を支持し、地雷の壊滅的な影響に、より緊急かつ決意を持って対処するという締約国の集団的な決意を強調するものである。

◇次回、第22 回締約国会議の議長国となる日本
日本政府は、2025 年に開催される第22 回締約国会議の議長国となる。議長を務めるのはジュネーブ軍縮会議の特命全権大使の市川とみ子氏だ。来年の会議は、シェムリアップ・アンコール行動計画の初年度の進捗を確認する大事な会議なる。今回の再検討会議で採択された政治宣言をより高いレベルで具現化していくようなリーダーシップを発揮することに期待したい。
ランドマインモニター 2024の主要点
2024年11月に開催された対人地雷全面禁止条約(オタワ条約)第5回再検討会議を前に、最新のランドマインモニター 2024が発行されました。
最新の報告書では、2023年に地雷の犠牲者が増加したことに注目しています。地雷禁止国際キャンペーン(ICBL)は、ミャンマー、ロシア他、オタワ条約に加盟していない国が地雷を使用し続けていることは、対人地雷を違法とする国際条約によって確立された規範を著しく歪める行為であると非難しています。
以下にランドマインモニター 2024の主要な点を記します。
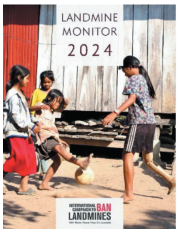
◇対人地雷全面禁止条約(オタワ条約)の現況
オタワ条約には合計164の締約国が加盟しているが、33の国はまだ加盟していない。この条約に最後に加盟した国は、ともに2017年に加盟したパレスチナとスリランカ。2023年、ロシアは、完全な普遍化とオタワ条約の効果的な実施を求める国連総会の年次決議に反対票を投じた史上初の国となった。
◇対人地雷の使用
対人地雷は、2023年半ばから2024年10月までの報告期間中に、ミャンマーとロシア、イラン、北朝鮮によって使用された。ロシアは2022年2月にウクライナに侵攻して以来、ウクライナで対人地雷を広範囲に使用しており、オタワ条約の締約国でない国が締約国の領土で対人地雷を使用するという未曾有の事態に至った。1999年に発効されて以来、ランドマインモニターは、毎年のようにミャンマー政府軍による対人地雷の新たな使用について記録している。少なくとも5カ国(コロンビア、インド、ミャンマー、パキスタン、パレスチナ(ガザ))の非国家武装集団(NSAG)も、報告期間中に対人地雷を使用した。
◇対人地雷の生産
対人地雷の開発、製造、取得を行う国として、オタワ条約に加盟していない、アルメニア、中国、キューバ、インド、パキスタン、ロシア、シンガポール、韓国、ベトナムなどの計12カ国がモニターのリストに残っている。うちインド、イラン、ミャンマー、パキスタン、ロシア、韓国は、対人地雷の開発や生産を積極的に行っているとみられる。
◇備蓄地雷の破壊と訓練目的での地雷の保持
地雷禁止条約の締約国164カ国のうち、これまでに94カ国が対人地雷の廃棄を公式に完了し、合計5,500万個以上の対人地雷が廃棄された。締約国であるギリシャとウクライナは、ともに対人地雷を未だに貯蔵している。両国はそれぞれの廃棄期限までに備蓄廃棄を完了できなかったため、オタワ条約第4条に違反している。2024年、ギリシャは対人地雷をクロアチアに移送し、破壊し始めたことを報告した。
合計63の締約国が訓練及び研究の目的で対人地雷を保有している。そのうちの2カ国、バングラデシュとフィンランドはそれぞれ12,000個以上の地雷を保有しており、他の23の国・地域はそれぞれ1,000個以上の地雷を保有している。2024年5月、スロバキアは対人地雷の保有がなくなったと報告した。
◇対人地雷・ERW(爆発性戦争残存物)不発弾による死傷者
世界で少なくとも58の国と地域が依然として対人地雷で汚染されている。
2023年には、少なくとも5,757人の地雷とERWの死傷者が記録された(死亡1,983人、負傷3,663人)。111人の死傷者について生存状況は不明。2023年には、53の国と2つの地域で地雷/ERWの死傷者が確認された。このうち、38カ国はオタワ条約の締約国。記録された全死傷者の84%(4,335人)を民間人が占めていた。また民間人犠牲者のうち37%(1,498人)は子どもだった。締約国ではないミャンマーは、2023年に初めて年間死傷者数(1,003人)を記録した。次に多かったのは過去3年間にわたり最も犠牲者の多かったシリア(933人)だった。以下アフガニスタン、ウクライナと続くがどちらも2023年に500人以上の死傷者が記録された。
◇地雷の除去
締約国は、2023年に合計281.50km²の汚染された土地を除去したと報告し、その結果、160,566個の対人地雷が破壊された。この数は、2019年の前回の再検討会議以降、締約国が安全を確保した最大の面積であり、2022年と比較して62.2km²の増加を表している。カンボジアとクロアチアは、2023年に最大の除去総数を報告。合計で209km²以上の土地を掃討し、24,743個の対人地雷を破壊した。
◇地雷危険回避教育
地雷除去義務を負う33の締約国のうち、28の締約国が、2023年に対人地雷汚染のリスクにさらされている人々に対して危険回避教育を提供したと報告している。リスクのあるグループには、遊牧民、狩猟者、羊飼い、農業労働者など、異なる空間を定期的に移動する人々が含まれていた。国内避難民(IDP)も同様の脅威に直面している。子どもは依然としてリスクが高い。
◇犠牲者支援
2023年、ヘルスケアとリハビリテーションサービスは資金不足のままで、多くの州で、特にアクセシビリティ、専門知識、活動基盤など複数の課題に直面した。アフガニスタン、南スーダン、スーダン、ウクライナ、イエメンなどの地雷犠牲者の多い締約国で、医療制度に大規模な混乱が生じた。生計支援が最も必要とされている多くの締約国において、経済的機会へのアクセスには大きな格差が残っている。心理的支援サービスは、一握りの締約国で利用可能であったが、これらのサービス、特にコミュニティベースのピアサポートは、国家保健予算に含まれることはめったになく、その影響と範囲は限られている。NGOはこのギャップを埋めるのに貢献している。
◇地雷対策支援
2023年、地雷対策に対する世界的な支援は総額10億3,000万米ドルだった。地雷対策のための年間資金が10億を超えたのはこれが初めてで、これはウクライナへの資金援助の増加が反映されている。34のドナーが地雷対策に7億9,830万ドルの国際支援を提供した。これは2022年に提供された金額と同額である。米国、ドイツ、欧州連合(EU)は、引き続き地雷対策に対する上位3つの資金提供者となった。ウクライナは2年連続で受益者リストのトップに立ち、3億810万ドルを受け取り、これはすべての国際ドナー資金の39%に相当する。国際的な地雷対策資金の半分は除去プログラムの支援に使われた。被害者支援に割り当てられた国際支援は合計4,700万ドルで、2022年の合計から25%増加したが、依然として地雷対策支援資金総額のわずか6%にすぎない。
(翻訳:清水俊弘)
クラスター爆弾禁止条約 第12回締約国会議報告
2024 年 9 月 10 日から 13 日にかけてジュネーブでクラスター爆弾禁止条約(CCM)第 12 回締約国会議が開催されました。(議長国はメキシコ)
今会議で、締約国は条約を普遍的に遵守することの重要性と、条約外の国によるクラスター爆弾の使用、開発、生産、貯蔵、移転を阻止する必要性を強調しました。これは、米国政府が過去 1 年間にウクライナにクラスター爆弾を複数回移転したことに照らして特に重要です。
以下、今回の締約国会議の概要です。
◇不発弾処理期限の延長リクエスト:
担当委員会は、ペルーと南アフリカを含むすべての締約国が昨年、備蓄廃棄(第 3 条)義務を完了したことを歓迎するとともに、ベルギーが訓練目的で保有していたすべてのクラスター爆弾の無力化を果たしたことを評価した。チャド、ドイツ、ラオスの 3 カ国が提出していた除去期限の延長申請は承認された。
◇リトアニアの撤退:
開会式に出席したすべての発言者と、一般討議の中で発言したほとんどの締約国が、リトアニアが条約を離脱するという決定と、これが国際人道法に及ぼす広範な影響について遺憾の意を表明し、その決定を再考するよう求めた。
◇条約の普遍化:
議長国による普遍化の取り組みに関する報告に続き、リトアニアの CCM からの離脱は、条約の規範を揺るがす危険な前例であると強調した。この問題については、クラスター兵器連合(CMC)も力強い声明を発表。注目すべき点は、コンゴ民主共和国(署名国)が批准プロセスを完了するための新たな努力について共有し、ジンバブエ ( 非署名国 ) は内部協議が進行中であり、現在、条約への参加を検討する意思があると発表したことだ。
◇保管と備蓄の破壊:
南アフリカとペルーは、自国の備蓄弾の廃棄完了を宣言し、現在の条約締約国による備蓄廃棄の義務が 100% 履行されたことを公式に示した。クラスター爆弾の備蓄を保有することで知られるキプロスとインドネシアに対し、遅滞なく条約を批准し、その備蓄について報告するよう求めた。CMC は、締約国、特にドイツによる米国のクラスター爆弾の保管と輸送の問題に激しく抗議した。
◇クラスター爆弾の不発弾の除去と廃棄、リスク教育:
モーリタニア、イラク、レバノン、チリ、ラオス人民民主共和国、ソマリアなど、以下の影響を受ける国々が、不発弾処理の進捗状況と課題に関する最新情報を提供した。CMC は、締約国に対し、不発弾処理とリスク教育に緊急性をもって行動するよう促し、同時に、将来の使用や新たな汚染を防止するためにあらゆる可能な措置を講じるよう求めた。
◇犠牲者支援:
:イラク、レバノン、ラオス、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナは、いずれも生存者に対する責任を負っており、犠牲者支援に関する彼らの取り組みと課題について最新情報を提供した。イラクとラオスでは、2024年に子どもを含む新たなクラスター爆弾の犠牲者が報告された。CMC は、締約国に対し、条約の犠牲者支援規定を履行することは道徳にも法的にも重要であると強調した。

◇国際協力と援助:
CMC は、世界中で不安定と紛争が増大する中、条約への締約国のコミットメントと協力と援助の提供がますます重要になっていることを強調した。ドナー国は、クラスター爆弾に関連する活動に関する資金援助の最新情報を共有し、被害を受けた国は、自国の計画やニーズ、他国による支援の提供を促進するために講じている措置について最新情報を提供した。
◇コンプライアンス:
この議題項目の下では、CMC とパナマのみが発言した。CMC は、懸念事項とする 3 つの主要な解釈問題についての見解を共有し、締約国に対し、以下の事項について意見を共有するよう求めた。
1. クラスター爆弾を使用する可能性のある非締約国と
の共同軍事作戦中の支援の禁止(「相互運用性」と呼ばれる問題)。
2. クラスター爆弾の輸送と外国からの備蓄の禁止。
3. クラスター爆弾製造への投資の禁止。
パナマは、締約国の領土を通るクラスター爆弾の通過に関する CMC の懸念に同調し、第 21 条の曖昧な解釈を非難した。また、対人地雷禁止条約の経験に沿って、第 1 条の実施に関する懸念に対処するために、次回の再検討会議(2026 年)でコンプライアンスに関する専門の作業部会を設立するという提案を繰り返した。
最終報告書:激しい交渉の結果、メキシコ議長国の確固たる姿勢のおかげで、NATO 諸国がリトアニアの撤退とクラスター爆弾の継続的な使用に関する文言を骨抜きにする意図があったにもかかわらず、最終報告書には、リトアニア離脱についての「深い遺憾の意」の表明、「いかなる関係者による、いかなる状況下でも、クラスター爆弾の使用を強く非難する」などの適切で直接的な文言が採択された。今回、締約国が示した連帯と決意は、同条約の将来の成功とクラスター爆弾の撲滅という使命のための強固な基盤となる。
(翻訳 清水俊弘)
クラスター兵器モニター 2024の主要点
2024 年 9 月に開催された、クラスター爆弾禁止条約第 12 回締約国会議を前に、最新のクラスター兵器モニターが発表されました。
クラスター爆弾による死傷者は、クラスター爆弾禁止条約の非加盟国であるミャンマー、シリア、ウクライナの 3 カ国で発生しています。2022 年 2 月にロシアがウクライナに全面侵攻して以来、ウクライナではクラスター爆弾による死傷者が 1,000 人以上を記録しています。
以下、クラスター兵器モニター 2024 の主要点です。

◇クラスター爆弾禁止条約(CCM)の現状
*条約には現在 112 の締約国と 12 の署名国が参加している。最後に加盟した国は 2023 年 8 月の南スーダンで、2023 年 2 月に批准したのはナイジェリア。
*リトアニアは 2024 年 7 月 26 日に法律を制定し、条約からの脱退を承認し、第 20 条に規定された手順に従ってから 6 カ月後に発効する。
* 2023 年 12 月、国連総会(UNGA)で同条約を推進する年次決議が採択され、CCM に加盟していない 37 カ国を含む 148カ国が参加したが、ロシアはそれに反対票を投じた唯一の国だった。
* 2023 年 7 月から 2024 年 4 月にかけて、ジョー・バイデン米大統領は、155mm 砲の弾道ミサイルで運搬される米国製のクラスター爆弾をウクライナに 5 回移送することを承認した。
◇クラスター爆弾の使用
クラスター爆弾は、2023 年から 2024 年 7 月にかけてロシア軍とウクライナ軍によってウクライナで使用され、ミャンマーとシリアでも新たな使用が記録されている。
2008 年 5 月に同条約が採択されて以来、どの締約国もクラスター爆弾の新たな使用に関する報告や申し立てはしていない。
◇クラスター爆弾による死傷者
*ウクライナは、2 年連続で年間死傷者数が世界で最も多かった。2022 年 2 月にロシアがウクライナに全面侵攻して以来、ウクライナではクラスター爆弾による死傷者が 1,000 人以上を記録している。
* 2023 年には、世界で 219 人がクラスター爆弾によって死傷した。
* 2023 年には、アゼルバイジャン、イラク、ラオス、レバノン、モーリタニア、ミャンマー、シリア、ウクライナ、イエメンの 9 カ国でクラスター爆弾による新たな死傷者が記録された。
*2023 年に報告された死傷者のうち、118 人がクラスター爆弾による攻撃によるもので、101 人がクラスター爆弾の不発弾によるものだった。
*2023年に記録された全死傷者の93%を民間人が占めている。
*子どもは、クラスター爆弾の子爆弾による被害を受けるリスクが特に高い。
* 2023 年のクラスター爆弾残骸による全死傷者のうち、子どもはほぼ半数(47%)を占めている。クラスター爆弾の不発弾による死傷者の大半は、イラクとレバノン、および非締約国であるシリアの子ども達だった。
◇備蓄弾の破壊と保持
* 2008 年に条約が採択されて以来、締約国は、自らが宣言したクラスター爆弾の備蓄を 100% 廃棄し、149万発のクラスター爆弾と 1 億 7,900万発の子弾を廃棄してきた。
*ブルガリア、スロバキア、南アフリカは 2023 年 9 月にそれぞれのクラスター爆弾の廃棄が完了したと発表し、ペルーは2023 年 12 月に貯蔵廃棄を完了した。
*許可された研究・訓練目的で実弾を保管しているのはわずか 10 カ国で、その中でもドイツが最も多い。ベルギーは 2023年中に、保有していたクラスター爆弾をすべて廃棄した。
◇クラスター爆弾の汚染とクリアランス
*クラスター爆弾の不発弾によって汚染されている、または汚染されている疑いのある国は合計 28 カ国で、この中にはアフガニスタン、チャド、チリ、ドイツ、イラク、ラオス、レバノン、モーリタニア、ソマリア、そして最新の締約国である南スーダンの 10 カ国が含まれている。
*締約国であるボスニア・ヘルツェゴビナは、2023 年 8 月にクラスター爆弾の不発弾の除去を完了し、クラスター爆弾禁止条約に基づく除去義務を果たす 9 番目の締約国となった。
* 2024 年上半期には、チャド、ドイツ、ラオスがそれぞれ現在の除去期限の延長を要請した。これらの要請は、第 12 回締約国会議で検討される。
◇犠牲者支援
*多くの締約国が依然として適切でアクセス可能なサービスを提供する上で大きな課題に直面している。アフガニスタンとレバノンの医療制度は深刻な危機に瀕しており、アフガニスタンの女性や少女、レバノンの難民の医療サービスへのアクセス制限が強まっている。
*被害者に対する社会経済的包摂と財政支援の進展は限定的であり、多くのニーズが満たされないままである。
◇クラスター爆弾の生産
* 2023 年以降、クラスター爆弾の生産国はブラジル、中国、エジプト、ギリシャ、インド、イラン、イスラエル、北朝鮮、韓国、パキスタン、ポーランド、ルーマニア、ロシア、シンガポール、トルコ、米国の 16 カ国にミャンマーが加わって 17カ国に増加した。いずれも条約の締約国ではない。
*クラスター爆弾モニターは、報告期間中にインド、ミャンマー、ロシア、韓国で新たなクラスター爆弾が製造された証拠を発見した。
(翻訳 : 清水俊弘)
「無力でもなく、ゴールでもない」
日本被団協ノーベル平和賞受賞に被爆地・長崎から見えるもの
橋場 紀子 長崎大学多文化社会学研究科後期博士課程、記者
厳かに響くファンファーレ。被爆地・長崎で報道記者として取材してきた被爆者や被爆二世がノルウェー・オスロでノーベル平和賞の受賞式に参列している。状況は全てわかっているはずなのに、それでも“理解や気持ちが追いつかない”、そんな何とも不思議な気持ちで 12 月10 日夜、晴れの大舞台を見つめていました。
思いもよらぬ受賞
ノーベル平和賞受賞の速報を日本被団協の多くのメンバーは、全国会議の帰路、交通機関の中で知ったそうです。これまでにも被団協や山口仙二さん(2013 年死去)、谷口稜曄さん(2017 年死去)などが、団体や個人としてノーベル平和賞にノミネートされました。しかし、吉報は届かず、被団協代表委員の田中重光さんいわく「皆、がっかりして諦めてしまっていた」のだそうです。しかし、後になって思うと、被爆 80 年を前にしての受賞は絶好のタイミングでした。一気に、被団協や被爆者が注目され、連日、取材の嵐。街で声をかけられることが増えたと聞きますし、被爆者を取り巻く雰囲気、風向きが変わったようにも感じられます。
受賞の意義とタイミング
被爆者への注目は、核兵器使用の脅威ともつながっていました。ウクライナやイスラエルでは戦火が止みません。一時は 8 万発もあった核兵器 ( 核弾頭 ) の数は 1 万2,520 発(去年 6 月、RECNA= 長崎大学核兵器廃絶研究センター)と格段に減りました。それでも 1 万発超。「核兵器と人類は共存できない」 「核兵器がなくなるまでは死んでも死にきれない」と谷口稜曄さんは何度も言っていました。その被爆者の平均年齢は 85.58 歳(去年 3 月末、厚生労働省)となり、「被爆者のいない時代の始まり」に私たちはいます。それなのに、核を使おうとする国。核を脅しに使おうとする国。さらには、核を持とうとする国。こうした核拡散、核への妄信をどうやって止めるのか、不安が渦巻いています。だからこそ受賞は、「被爆体験を語り続け、核兵器廃絶を訴えてきたその積み重ねの先にこの受賞があったのだ」 「決して無力ではないんだ」と、被爆者や平和活動を続ける市民を大いに励ましました。
そこにいない人たちへ
しかし、そもそも私たちが知る“被爆者”とは、平和教育や反核運動などで「語られた」(それも生々しく凄惨な)被爆体験によって知られています。あの日広島や長崎で即死した人たち、その後被爆による傷や病気で次々と命を失った人たち、朝鮮半島や北南米などで暮らす「在外被爆者」と呼ばれる人たちの“声なき声”があることを、改めて思いました。毎夏の平和祈念式典で首相は「唯一の戦争被爆国」とあいさつで繰り返しながら、原爆の被害は 80 年が経とうとしても全容は分かりません。授賞式のスピーチで田中熙巳さんが繰り返したように国家補償もされていません。
ノーベル平和賞は確かに喜ばしく、輝かしく、こういう日が来るのだな、と胸が熱くなる思いです。それでも、まだ核兵器がなくなったわけではありません。ノーベル平和賞がゴールでもありません。この華やかな舞台の光が強ければ強いほど、その影の部分に目を凝らしてしっかりと見つめ続けなければいけない。そして、今度は被爆地から、“被爆国”から戦争や核兵器をなくす取り組みは決して無力ではないのだ、というメッセージを伝え広げていく。そんな思いを強くする被爆80年の始まりです。
JCBL事務局だより
ミャンマーの子どもたちを地雷から守りたい
2024年11月、JCBLが支援するDKK(Dove KK)による地雷の危険回避教育活動が始まりました。
ICBL/CMCが発行したランドマインモニター2024によると、2023年にミャンマーで地雷で死傷した人々の数は1,003人。2022年の3倍に上りました。これは世界でも最も多い数字であり、このうち子どもの犠牲者は全体の1/4に及びます。
昨年から増加の一途を辿る地雷犠牲者を少しでも減らすために、JCBLとDKKは今年度地雷の危険回避教育の教材作りと、教育活動に力を入れていくことにしました。
9月にバンコクで打ち合わせをしてから僅か2カ月足らずで教材制作を進め、乾季の入り口である11月に間に合わせたDKKの機動力には目を見張るものがあります。
出来あがったポスターをはじめとした教材は、避難民のいる地域や、彼ら・彼女らの行動範囲に貼り出され、地雷や不発弾に注意を促しています。
この活動の目標として次の3つを掲げています。
1.地雷・不発弾の危険性についてコミュニティの人々の意識を高める
2. 犠牲者が出た場合の対応・報告体制など、コミュニティの中での情報共有や医療機関との連携を確認する
3. 積極的な教育を通じて事故の発生率を下げる
そのために、地雷のリスクや安全確保について議論するワークショップを開催したり、訓練を受けたトレーナーとサバイバーが主導するセミナーを学校、診療所、修道院、地元のコミュニティオフィスで行っていきます。
また、皆が教材の内容を理解するために、資料が民族言語で作られていることも大事な要素です。この活動の成果は次で報告させていただく予定です。
代表理事 清水 俊弘

